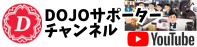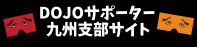歴史上、君臣の分義を厳かに守るために、
皇籍復帰が斥けられた実例を1つ、紹介する。
南北朝時代の貴族にして和学者、四辻善成(よつつじよしなり)
という人物がいた。
源氏物語の注釈書『河海抄(かかいしょう)』の著者として知られる。
第84代順徳天皇の皇子善統親王の孫で、
尊雅王の子(天皇から3世)。
31歳で皇籍を離れて源姓を賜り、北朝に仕えた。
祖父が四辻宮と号されたので、四辻を名乗った。
晩年、足利義満の大叔父(外祖母の弟)として優遇され、
70歳で左大臣にまで上り詰めた(応永2年、1395)。
調子に乗った善成は親王宣下、つまり皇籍への復帰も望んだ。
しかし、いかに元皇籍にあった人物でも、
既に臣下となって40年もの歳月を経ている。
そこで「もはや皇胤とは見なし難い」として、
室町幕府の執事・管領を務めた
有力武将、斯波義将(しばよしゆき、「よしまさ」とも)が諫めて、
そのまま出家させたという。
君臣のケジメを曖昧にしないためであり、
誰もが違和感を覚える振る舞いだったのだろう。
なお付言しておくと、義将は足利義満の死後、
前関白一条経嗣らの計らいで、義満が生前強く望んでいた
「太上天皇」の尊号が朝廷から贈られた時も、
将軍義持に説いて即日、辞退させた。
当時、太政官外記(げき)局の最上位にいた中原師胤(もろたね)は、
「臣下で太上天皇の尊号を得た例はない」と明言している。
従って、義将は四辻善成の場合と同様、
当時の「当然の常識」に立脚して対処したに過ぎないだろう。
しかし、たとえ当然の常識であっても、
それをこうした場面で公然と貫くには、
然るべき勇気と政治的力量が必要だったはずだ。
わが国の歴史には、こうした人物が幾人も現れ、
君臣の別を大切に守って来たのである。